グラブル以外のことも書く。
最近勉強については言及をしていなかったが、
少しずつやっていた古文書入門のテキストが最後まで終わった。
テキストの内容は以下の様なものであった。
- 離縁状(江戸時代)
- 通行手形(江戸時代)
- 戦国武将の手紙(桃山時代)
- 明治維新の有名人の手紙(江戸時代末)
1巻、2巻の離縁状や通行手形は、ある程度文書としての定形がある。
内容も一般人に関係するもので、内容が類推でき、そこから読み解ける部分もあった。楽しい。
3巻になると、急に難易度が上がる。
単語もむずかしいが、当て字を使うわ、そもそも文字自体が
祐筆という文書書きのプロが書いているせいか、読みにくい(気がする)。
1行の文字数が統一されていて、文の終わりが平気で行の途中にあったり、
文書としての見た目の美しさが重要視されているように感じた。
この3巻の冒頭、信長の手紙がメチャメチャに難しく、一度挫折しかけた。
ドラマとかで、文書が届いてすぐに開封して読み上げてるシーン。
よく見かけるけど、本当にスラスラ読めてたんか?
最終4巻はさぞ難しいかと思いきや、ひらがなが出てきて、大部分は読みやすかった。
(漢字だが、平仮名として読む場合があるということで、難しい要素ではある)
坂本龍馬は特に好きではなかったが、今回出てきた手紙の文章が読みやすく好感を抱く。
それにしても、150年前はこんなふうに文章を書いて相互に解読できていたっていうのが未だに信じられん。変体仮名や合字も出てくるしアーイキソ。
趣味講座だが、せっかく一通り終わったので、1月の古文書検定を受けてみることにした。
これが何の役に立つのとか、そういうことは考えてはいけない。
手順が分かりにくいが、パンフレットを申し込むと、
郵便局の振込用紙が配送されてくる。面倒くさい。
3級は4000円。
高いので落ちたら再受験しない。
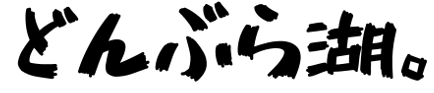



コメント